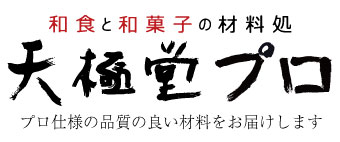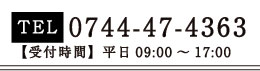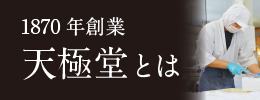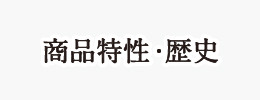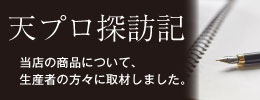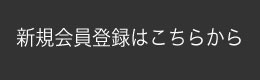商品特性・歴史
柏餅のいろは

柏餅の起源
こどもの日(端午の節句)の定番和菓子として親しまれている柏餅。
上新粉や白玉粉で作った白いお餅と、鮮やかな緑の柏葉のコントラストが春らしい一品です。
柏の葉は古い時代から、食べ物の器として活用されていました。 また、『枕草子』や『源氏物語』などの文献では、柏の木に樹木を守護する神「葉守」が宿ると記されています。 柏という植物が古くから人の生活に身近なもので、なおかつ神聖視されていた事が窺えますね。
通常の植物は、古い葉が全て落ちてから新芽を出します。ですが、柏は新芽が出るまで古い葉が落ちません。このような特徴から転じて、「子供が生まれるまで親は死なない」「跡継ぎが絶えない」、ひいては「子孫繁栄」に関する縁起物として扱われるようになりました。
柏餅が食されるようになったのは江戸時代。子孫を絶やさず家系が続く事を重要視する武家社会において、柏餅は縁起物として申し分ない和菓子だったのでしょう。
柏の葉は古い時代から、食べ物の器として活用されていました。 また、『枕草子』や『源氏物語』などの文献では、柏の木に樹木を守護する神「葉守」が宿ると記されています。 柏という植物が古くから人の生活に身近なもので、なおかつ神聖視されていた事が窺えますね。
通常の植物は、古い葉が全て落ちてから新芽を出します。ですが、柏は新芽が出るまで古い葉が落ちません。このような特徴から転じて、「子供が生まれるまで親は死なない」「跡継ぎが絶えない」、ひいては「子孫繁栄」に関する縁起物として扱われるようになりました。
柏餅が食されるようになったのは江戸時代。子孫を絶やさず家系が続く事を重要視する武家社会において、柏餅は縁起物として申し分ない和菓子だったのでしょう。
柏葉に秘められた役割
上で紹介した験担ぎ以外にも、柏の葉で餅を巻くのには様々な理由があります。
餅の乾燥を防ぐための保湿手段、直接手で持って食べる際に汚れないように、香り付けのために…等々。
海のない奈良県において、山々を越えて輸送されてくる鯖は非常に貴重なものでした。そのため、「柿の葉寿司」は祭事や祝い事の席でのみ振る舞われるご馳走でもありました。
ちなみに柏の葉は固く、筋が残りやすいため食用には向いていません。 桜餅のように葉まで食べようとする方もままいらっしゃいますが、当店では剥がして餅だけお召し上がりいただくのをお勧めしています。
こどもの成長への願いが込められた柏餅。当店では柏葉の販売のほか、餅の材料になる上新粉・白玉粉の販売やレシピ公開も行なっております。
レシピページから各商品の詳細をご確認いただけますので、是非ご覧くださいね。
海のない奈良県において、山々を越えて輸送されてくる鯖は非常に貴重なものでした。そのため、「柿の葉寿司」は祭事や祝い事の席でのみ振る舞われるご馳走でもありました。
ちなみに柏の葉は固く、筋が残りやすいため食用には向いていません。 桜餅のように葉まで食べようとする方もままいらっしゃいますが、当店では剥がして餅だけお召し上がりいただくのをお勧めしています。
こどもの成長への願いが込められた柏餅。当店では柏葉の販売のほか、餅の材料になる上新粉・白玉粉の販売やレシピ公開も行なっております。
レシピページから各商品の詳細をご確認いただけますので、是非ご覧くださいね。
- 2023.06.19
- 11:57
- 商品特性・歴史