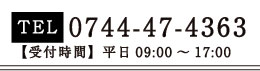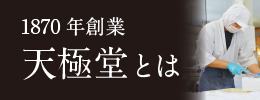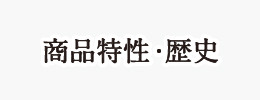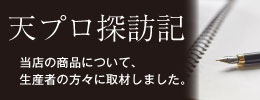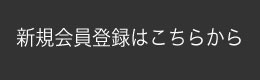レシピ
ふんわりだし巻き卵
エアードライ(温風乾燥)という手法で加工した山芋を粉砕し、便利なパウダー状に仕上げた『山芋パウダー』。
山芋特有の風味や粘りは損なわず、皮むきやすりおろしなどの手間を省ける優れものです。
水で戻してうどんや蕎麦にかけたり、お好み焼きなどの粉物料理に混ぜたりするのがスタンダードな活用法ですが、他にも様々な料理にご活用いただけます。
今回ご紹介するのは『山芋入りだし巻き卵』のレシピ。山芋パウダーを加えると、いつもよりふんわりとした仕上がりに。
山芋特有の風味や粘りは損なわず、皮むきやすりおろしなどの手間を省ける優れものです。
水で戻してうどんや蕎麦にかけたり、お好み焼きなどの粉物料理に混ぜたりするのがスタンダードな活用法ですが、他にも様々な料理にご活用いただけます。
今回ご紹介するのは『山芋入りだし巻き卵』のレシピ。山芋パウダーを加えると、いつもよりふんわりとした仕上がりに。

材料(2人前)
山芋パウダー:10g
水:大さじ2
卵:3個
白だし:大さじ1
サラダ油:適量
水:大さじ2
卵:3個
白だし:大さじ1
サラダ油:適量
作り方
調理
①山芋パウダーと水を混ぜて基本のとろろを作ります。
②ボウルに卵を割り入れ、①と白だしを入れてよく混ぜます。
③だし巻き卵を作ります。
①山芋パウダーと水を混ぜて基本のとろろを作ります。
②ボウルに卵を割り入れ、①と白だしを入れてよく混ぜます。
③だし巻き卵を作ります。
山芋を加える事で生地が破れにくくなり、初心者の方でも簡単にだし巻き卵を作る事が出来ます。
- 2023.06.18
- 22:23
山芋入り鶏つくね
エアードライ(温風乾燥)という手法で加工した山芋を粉砕し、便利なパウダー状に仕上げた『山芋パウダー』。
山芋特有の風味や粘りは損なわず、皮むきやすりおろしなどの手間を省ける優れものです。
水で戻してうどんや蕎麦にかけたり、お好み焼きなどの粉物料理に混ぜたりするのがスタンダードな活用法ですが、他にも様々な料理にご活用いただけます。
今回ご紹介するのは『山芋入り鶏つくね』のレシピ。山芋パウダーを加えると、冷めてもふんわりとした仕上がりに。
山芋特有の風味や粘りは損なわず、皮むきやすりおろしなどの手間を省ける優れものです。
水で戻してうどんや蕎麦にかけたり、お好み焼きなどの粉物料理に混ぜたりするのがスタンダードな活用法ですが、他にも様々な料理にご活用いただけます。
今回ご紹介するのは『山芋入り鶏つくね』のレシピ。山芋パウダーを加えると、冷めてもふんわりとした仕上がりに。

材料(2人前)
山芋パウダー:20g
水:大さじ4
生姜:6g
鶏ひき肉:140g
レンコン:100g
大葉:4枚
酒・片栗粉:各大さじ1
ごま油:大さじ1
醬油・砂糖・みりん:各大さじ1
水:大さじ4
生姜:6g
鶏ひき肉:140g
レンコン:100g
大葉:4枚
酒・片栗粉:各大さじ1
ごま油:大さじ1
醬油・砂糖・みりん:各大さじ1
作り方
調理
①山芋パウダーと水を混ぜて基本のとろろを作ります。
②生姜・レンコン・大葉をみじん切りにします。
③ボウルに鶏ひき肉、①、②、酒、片栗粉を入れて良く練り混ぜ、6等分にして丸めます。
④フライパンで油を熱し③を両面焼いて火を通します。
⑤④に醤油・砂糖・みりんを入れて少し煮詰めたら、ネギと胡麻をふりかけて完成です。
①山芋パウダーと水を混ぜて基本のとろろを作ります。
②生姜・レンコン・大葉をみじん切りにします。
③ボウルに鶏ひき肉、①、②、酒、片栗粉を入れて良く練り混ぜ、6等分にして丸めます。
④フライパンで油を熱し③を両面焼いて火を通します。
⑤④に醤油・砂糖・みりんを入れて少し煮詰めたら、ネギと胡麻をふりかけて完成です。
- 2023.06.18
- 22:23
山芋のポタージュ
エアードライ(温風乾燥)という手法で加工した山芋を粉砕し、便利なパウダー状に仕上げた『山芋パウダー』。
山芋特有の風味や粘りは損なわず、皮むきやすりおろしなどの手間を省ける優れものです。
水で戻してうどんや蕎麦にかけたり、お好み焼きなどの粉物料理に混ぜたりするのがスタンダードな活用法ですが、他にも様々な料理にご活用いただけます。
今回ご紹介するのは『山芋のポタージュ』のレシピ。とろみのついた温かさが体を優しく温めます。
山芋特有の風味や粘りは損なわず、皮むきやすりおろしなどの手間を省ける優れものです。
水で戻してうどんや蕎麦にかけたり、お好み焼きなどの粉物料理に混ぜたりするのがスタンダードな活用法ですが、他にも様々な料理にご活用いただけます。
今回ご紹介するのは『山芋のポタージュ』のレシピ。とろみのついた温かさが体を優しく温めます。

材料(1人前)
山芋パウダー:10g
牛乳:150cc
コンソメ:小さじ1/2
塩胡椒:少々
トッピング類(オリーブオイル・パセリ・クルトン等):適量
牛乳:150cc
コンソメ:小さじ1/2
塩胡椒:少々
トッピング類(オリーブオイル・パセリ・クルトン等):適量
作り方
調理
①山芋パウダー、牛乳、コンソメをミキサーに入れて攪拌します。
②①を小鍋に入れてかき混ぜながら温め、塩胡椒で味を調えます。
③器に盛り、オリーブオイル・パセリ・クルトンを散らせば出来上がり。
①山芋パウダー、牛乳、コンソメをミキサーに入れて攪拌します。
②①を小鍋に入れてかき混ぜながら温め、塩胡椒で味を調えます。
③器に盛り、オリーブオイル・パセリ・クルトンを散らせば出来上がり。
山芋特有のとろみはポタージュにぴったり。
体を芯からゆっくり温めてくれます。
体を芯からゆっくり温めてくれます。
- 2023.06.19
- 11:54
もち米で作る草餅
こんにちは!天極堂プロスタッフです。
今回ご紹介するのは、よもぎともち米を使った『草餅』のレシピ!
上新粉と餅粉でつくる草餅がさっくり歯切れの良い食感なのに対して、もち米でつくる草餅はもちもち柔らかな食感が特徴です。
香りのよい『冷凍よもぎ』『よもぎペースト』を使用しています。
今回ご紹介するのは、よもぎともち米を使った『草餅』のレシピ!
上新粉と餅粉でつくる草餅がさっくり歯切れの良い食感なのに対して、もち米でつくる草餅はもちもち柔らかな食感が特徴です。
香りのよい『冷凍よもぎ』『よもぎペースト』を使用しています。

材料(もち米を一升使用する場合)
もち米: 一升(=10合=約1.5kg)
『よもぎペースト』または『冷凍よもぎ』:500g(全体重量の25%)
餅とり粉:適量
『よもぎペースト』または『冷凍よもぎ』:500g(全体重量の25%)
餅とり粉:適量
作り方
準備
もち米は調理の前日の夜頃から冷水に浸け、吸水させておきます。
(今回は13時間ほど吸水させました。夏場は水温が上昇してしまうので、こまめに水を取り替えるか、冷蔵庫に入れて吸水させてください。)
よもぎペーストもしくは冷凍よもぎは、使用する分だけあらかじめ解凍し、汁を軽く絞ってください。
※解凍方法は流水解凍もしくは自然解凍をしてください。湯煎での解凍も可能です(目安時間15分)。※よもぎの汁を絞りすぎると香りが薄くなる可能性がございます。
もち米は調理の前日の夜頃から冷水に浸け、吸水させておきます。
(今回は13時間ほど吸水させました。夏場は水温が上昇してしまうので、こまめに水を取り替えるか、冷蔵庫に入れて吸水させてください。)
よもぎペーストもしくは冷凍よもぎは、使用する分だけあらかじめ解凍し、汁を軽く絞ってください。
※解凍方法は流水解凍もしくは自然解凍をしてください。湯煎での解凍も可能です(目安時間15分)。※よもぎの汁を絞りすぎると香りが薄くなる可能性がございます。
調理
①吸水が終わったもち米の水を切り、餅つき機に入れて蒸します。
②5~6分ほど餅をついてから、汁を軽く絞った解凍済みの『冷凍よもぎ』もしくは『よもぎペースト』を加えてください。
③はじめは適宜しゃもじで混ぜ、よもぎの混ざり具合に偏りがないようにします。
④もち米の粒がなくなり、生地がまとまって粘りが出れば捏ね上がりです。
⑤餅とり粉をまぶした大きめのバット・トレーなどに捏ねあがったもち生地を移します。
⑥もち生地の表面にも餅とり粉を薄くまぶし、餅とり粉をつけた手でもち生地を適量ずつちぎっていきます。
⑦ちぎった餅の形をきれいに整えれば完成!お好みで餡子やきな粉を添えてお召し上がりください。
①吸水が終わったもち米の水を切り、餅つき機に入れて蒸します。
②5~6分ほど餅をついてから、汁を軽く絞った解凍済みの『冷凍よもぎ』もしくは『よもぎペースト』を加えてください。
③はじめは適宜しゃもじで混ぜ、よもぎの混ざり具合に偏りがないようにします。
④もち米の粒がなくなり、生地がまとまって粘りが出れば捏ね上がりです。
⑤餅とり粉をまぶした大きめのバット・トレーなどに捏ねあがったもち生地を移します。
⑥もち生地の表面にも餅とり粉を薄くまぶし、餅とり粉をつけた手でもち生地を適量ずつちぎっていきます。
⑦ちぎった餅の形をきれいに整えれば完成!お好みで餡子やきな粉を添えてお召し上がりください。

食べてみた
まだ温かいつきたての柔らかなもちもち食感がたまりません!冷めたあとは少ししっかりした噛み応えも楽しめます。
今回は少し趣向を変えて、白餡を包んでみました。ぜんざいに入れたりこんがり焼いたり、様々な食べ方でお楽しみいただけます。
今回は少し趣向を変えて、白餡を包んでみました。ぜんざいに入れたりこんがり焼いたり、様々な食べ方でお楽しみいただけます。
- 2025.02.06
- 10:04
亥の子餅
皆様は"亥の子の日"をご存じでしょうか?
亥の子の日とは、旧暦10月の初めの亥の日の事。亥の子の日に行なわれる年中行事を"亥の子の祝い"と呼び、その行事の中で食べられていた餅菓子を"亥の子餅"といいます。
その名の通り、イノシシのこどものような見た目が特徴の亥の子餅。
焼き印の有無、求肥や餡子に加える食材などは地域によって異なりますが、今回はシンプルな仕上がりを目指して作りました。
亥の子の日とは、旧暦10月の初めの亥の日の事。亥の子の日に行なわれる年中行事を"亥の子の祝い"と呼び、その行事の中で食べられていた餅菓子を"亥の子餅"といいます。
その名の通り、イノシシのこどものような見た目が特徴の亥の子餅。
焼き印の有無、求肥や餡子に加える食材などは地域によって異なりますが、今回はシンプルな仕上がりを目指して作りました。

材料(12個分)
白玉粉:120g
シナモン:小さじ1
水:225ml
上白糖:170g
黒胡麻:3g
水飴:大さじ1
餡子:300g(今回はこしあんを使用しました)
胡桃:適量
片栗粉:適量
シナモン:小さじ1
水:225ml
上白糖:170g
黒胡麻:3g
水飴:大さじ1
餡子:300g(今回はこしあんを使用しました)
胡桃:適量
片栗粉:適量
作り方
準備
上白糖はあらかじめふるっておきます。
片栗粉はバットにふるっておきます。
上白糖はあらかじめふるっておきます。
片栗粉はバットにふるっておきます。
調理
①胡桃を砕き、餡子に混ぜ込みます。
②①を12等分に分け、丸めておきます。
③耐熱ボウルに白玉粉とシナモンを入れ、水を少しずつ加えながら混ぜます。ダマが残らないよう、全体がなめらかになるまでよく混ぜてください。
④上白糖と黒胡麻を加え、さらに混ぜ合わせます。
⑤鍋に④を加え、焦げ付かないようよく混ぜながら弱火で加熱します。
⑥全体に熱が通り、もっちりと固まってきたら火を止め、水飴を加えて全体的に練り上げます。冷めないよう手早く行なってください。
⑦⑥を一塊のまま、鍋から片栗粉をふるったバットの上に取り出し、上からも片栗粉をふるいかけます。
⑧常温で粗熱をとり、スケッパーなどで12等分に切り分けます。
⑨平らになるよう成形し、片面の片栗粉を払います。
⑩片栗粉を払った面に丸めておいた餡子を置き、包みます。
⑪餡子を包めたら外側に再度片栗粉をまぶし、形を楕円形に整えたら完成!片栗粉は食べる直前に払い落としてください。
①胡桃を砕き、餡子に混ぜ込みます。
②①を12等分に分け、丸めておきます。
③耐熱ボウルに白玉粉とシナモンを入れ、水を少しずつ加えながら混ぜます。ダマが残らないよう、全体がなめらかになるまでよく混ぜてください。
④上白糖と黒胡麻を加え、さらに混ぜ合わせます。
⑤鍋に④を加え、焦げ付かないようよく混ぜながら弱火で加熱します。
⑥全体に熱が通り、もっちりと固まってきたら火を止め、水飴を加えて全体的に練り上げます。冷めないよう手早く行なってください。
⑦⑥を一塊のまま、鍋から片栗粉をふるったバットの上に取り出し、上からも片栗粉をふるいかけます。
⑧常温で粗熱をとり、スケッパーなどで12等分に切り分けます。
⑨平らになるよう成形し、片面の片栗粉を払います。
⑩片栗粉を払った面に丸めておいた餡子を置き、包みます。
⑪餡子を包めたら外側に再度片栗粉をまぶし、形を楕円形に整えたら完成!片栗粉は食べる直前に払い落としてください。
食べてみた

シナモンの爽やかな香りと餡子の甘みが相性抜群。このレシピではこしあんを使用しましたが、粒あんでも美味しく作れます。
求肥に練り込んだ胡麻や餡子に混ぜ込んだ胡桃の食感も楽しく、飽きが来ない一品です。
求肥は冷めるにつれ固くなり、作業の難易度が増してしまいます。⑥~⑩までの作業はとにかくスピード勝負になりますので、慣れないうちは少量ずつ作った方が美味しく綺麗に仕上がるかもしれません。
求肥に練り込んだ胡麻や餡子に混ぜ込んだ胡桃の食感も楽しく、飽きが来ない一品です。
求肥は冷めるにつれ固くなり、作業の難易度が増してしまいます。⑥~⑩までの作業はとにかくスピード勝負になりますので、慣れないうちは少量ずつ作った方が美味しく綺麗に仕上がるかもしれません。
- 2023.06.19
- 11:58
笹餅(七夕餅)
7月7日の七夕には、織姫と彦星の物語にあやかった様々な風習が残っています。
短冊に願い事を書いたり笹に飾りつけをしたりするのが定番ですね。
ひな祭りのちらし寿司やこどもの日の柏餅ほど定着はしていないようですが、七夕にはそうめんを食べるのが千年も前からの定番だったようです。
今回ご紹介する《笹餅(七夕餅)》もまた、七夕に食する伝統的な和菓子の一つ。今回は一口サイズで作ってみました。
短冊に願い事を書いたり笹に飾りつけをしたりするのが定番ですね。
ひな祭りのちらし寿司やこどもの日の柏餅ほど定着はしていないようですが、七夕にはそうめんを食べるのが千年も前からの定番だったようです。
今回ご紹介する《笹餅(七夕餅)》もまた、七夕に食する伝統的な和菓子の一つ。今回は一口サイズで作ってみました。

材料(20個分)
上新粉:200g
白玉粉:100g
砂糖:30g
ぬるま湯:210ml
餡子:100g
笹の葉:20枚
白玉粉:100g
砂糖:30g
ぬるま湯:210ml
餡子:100g
笹の葉:20枚
作り方
調理
①上新粉・白玉粉・砂糖をボウルに入れ、混ぜます。
②よく混ざったらぬるま湯を加え、菜箸で混ぜます。
③生地がぬるま湯を吸収してぽろぽろになってきたら、ひとまとまりになるまで手でこねます。
④生地がまとまったら一口大にちぎり、蒸し器に並べて中火で10分ほど蒸します。
⑤蒸し上がったら熱いうちにボウルに移し、すりこぎや麺棒を使って生地を潰すようにしてよくこねます。
⑥再び生地がまとまったら20等分に分けます。
⑦生地を円形に伸ばし、中心に餡子を乗せてくるむように包みます。
⑧カップ状に折った笹に餅を入れれば完成!
①上新粉・白玉粉・砂糖をボウルに入れ、混ぜます。
②よく混ざったらぬるま湯を加え、菜箸で混ぜます。
③生地がぬるま湯を吸収してぽろぽろになってきたら、ひとまとまりになるまで手でこねます。
④生地がまとまったら一口大にちぎり、蒸し器に並べて中火で10分ほど蒸します。
⑤蒸し上がったら熱いうちにボウルに移し、すりこぎや麺棒を使って生地を潰すようにしてよくこねます。
⑥再び生地がまとまったら20等分に分けます。
⑦生地を円形に伸ばし、中心に餡子を乗せてくるむように包みます。
⑧カップ状に折った笹に餅を入れれば完成!
食べてみた
上新粉と白玉粉を混ぜて作る餅は、もちもちした柔らかさと歯切れの良さのバランスが絶妙。
白玉粉で弾力が付いた分、餅の整形は少し難しくなります。しっかりこねて、なるべく熱いうちに作業をするのがオススメです。火傷には重々お気をつけて。
包みにくいようであれば餡子の量は減らしても大丈夫です。
白玉粉で弾力が付いた分、餅の整形は少し難しくなります。しっかりこねて、なるべく熱いうちに作業をするのがオススメです。火傷には重々お気をつけて。
包みにくいようであれば餡子の量は減らしても大丈夫です。
- 2022.03.22
- 10:07
よもぎのアイス
「ハーブの女王」と呼ばれるよもぎ。その名に恥じぬ効能の多さと香りの良さが古くから重用されてきた植物です。
日本になじみ深い植物ゆえに和菓子のイメージが強いよもぎですが、もちろん洋菓子にも美味しくご活用いただけます。
今回ご紹介するのは夏に食べたい「よもぎのアイス」。ミントよりもやさしい爽やかな香りで、夏の暑さを吹き飛ばしてくれる一品です。
日本になじみ深い植物ゆえに和菓子のイメージが強いよもぎですが、もちろん洋菓子にも美味しくご活用いただけます。
今回ご紹介するのは夏に食べたい「よもぎのアイス」。ミントよりもやさしい爽やかな香りで、夏の暑さを吹き飛ばしてくれる一品です。

材料
至高のよもぎ(よもぎパウダー):小さじ1.5
牛乳:100ml
生クリーム:100ml
卵:1個
砂糖:50g
牛乳:100ml
生クリーム:100ml
卵:1個
砂糖:50g
作り方
調理
①牛乳を弱火にかけて沸騰直前で火を止め、粗熱をとる。
②ある程度冷ましたらよく溶いた卵を加え、弱火にかける。
③とろみがついてきたら火からおろし、ザルなどで濾して再び粗熱をとる。
④ボウルに生クリームと砂糖を入れ、とろみがつくまで泡立てる。
⑤③を加えて混ぜ合わせ、バットなどに流し込んでラップをかけ、1時間ほど冷凍庫で冷やす。
⑥冷凍庫から一度取り出し、全体をかき混ぜてから平らに均す。
⑦ラップをかけて冷凍庫でさらに1時間~1.5時間ほど冷やし、十分に固まったら器に盛り付けて完成。
①牛乳を弱火にかけて沸騰直前で火を止め、粗熱をとる。
②ある程度冷ましたらよく溶いた卵を加え、弱火にかける。
③とろみがついてきたら火からおろし、ザルなどで濾して再び粗熱をとる。
④ボウルに生クリームと砂糖を入れ、とろみがつくまで泡立てる。
⑤③を加えて混ぜ合わせ、バットなどに流し込んでラップをかけ、1時間ほど冷凍庫で冷やす。
⑥冷凍庫から一度取り出し、全体をかき混ぜてから平らに均す。
⑦ラップをかけて冷凍庫でさらに1時間~1.5時間ほど冷やし、十分に固まったら器に盛り付けて完成。
食べてみた
牛乳のまろやかな味わいとよもぎの香りが見事に調和して、しっかり甘いけど甘すぎず、どこかスッキリとした後味のアイスクリームになりました。
お好みで細かく砕いたチョコレートなどを加えても美味しくなりそうです。
今回は『至高のよもぎ(よもぎパウダー)』を使用したレシピをご案内しましたが、他のよもぎ関連商品でも問題なくお作りいただけます。その際は好みに合わせてよもぎの分量を調節してみてくださいね。
お好みで細かく砕いたチョコレートなどを加えても美味しくなりそうです。
今回は『至高のよもぎ(よもぎパウダー)』を使用したレシピをご案内しましたが、他のよもぎ関連商品でも問題なくお作りいただけます。その際は好みに合わせてよもぎの分量を調節してみてくださいね。
- 2022.03.22
- 11:35
水無月
6月30日に執り行なわれる”夏越の祓”(なごしのはらえ)にあわせて食される「水無月」。
三角形のういろうの上にあずきや甘納豆をあしらった、見た目が特徴的な和菓子です。
ういろう部分の材料はお店や地域によって様々ですが、今回は天極堂の看板商品である吉野本葛と当店で取り扱っている白玉粉、そして薄力粉を使ったレシピをご紹介いたします。
三角形のういろうの上にあずきや甘納豆をあしらった、見た目が特徴的な和菓子です。
ういろう部分の材料はお店や地域によって様々ですが、今回は天極堂の看板商品である吉野本葛と当店で取り扱っている白玉粉、そして薄力粉を使ったレシピをご紹介いたします。

材料
吉野本葛:25g
白玉粉:30g
薄力粉:35g
砂糖:70g
水:160cc
茹で小豆/甘納豆:150g
白玉粉:30g
薄力粉:35g
砂糖:70g
水:160cc
茹で小豆/甘納豆:150g
作り方
調理
①吉野本葛・白玉粉・薄力粉・砂糖をボウルに入れ、混ぜます。
②よく混ざったら水を少しずつ加え、さらに混ぜます。
③ある程度混ぜた②をザルなどで濾す。全体的に溶け残りが無くなって綺麗な液状になるまで濾す作業を続ける。
④綺麗に濾した液を大さじ2杯分だけ別のボウルに移し、大さじ一杯の水(分量外)と混ぜ合わせます。
⑤残りの液を水で濡らした流し缶(無ければ調理用バットや耐熱タッパーでもOK)に流し入れ、あらかじめ湯を沸かし蒸気を上げておいた蒸し器の中に入れて、表面が固まるまで強火で10分ほど蒸します。
⑥表面が固まったら茹で小豆を乗せ、さらにその上から④を流し入れます。
⑦蒸し器に戻してさらに15分ほど蒸し上げます。
⑧十分冷めたら型から外し、三角形に切り分けます。冷蔵庫で冷やした方がより美味しくお召し上がりいただけます。
①吉野本葛・白玉粉・薄力粉・砂糖をボウルに入れ、混ぜます。
②よく混ざったら水を少しずつ加え、さらに混ぜます。
③ある程度混ぜた②をザルなどで濾す。全体的に溶け残りが無くなって綺麗な液状になるまで濾す作業を続ける。
④綺麗に濾した液を大さじ2杯分だけ別のボウルに移し、大さじ一杯の水(分量外)と混ぜ合わせます。
⑤残りの液を水で濡らした流し缶(無ければ調理用バットや耐熱タッパーでもOK)に流し入れ、あらかじめ湯を沸かし蒸気を上げておいた蒸し器の中に入れて、表面が固まるまで強火で10分ほど蒸します。
⑥表面が固まったら茹で小豆を乗せ、さらにその上から④を流し入れます。
⑦蒸し器に戻してさらに15分ほど蒸し上げます。
⑧十分冷めたら型から外し、三角形に切り分けます。冷蔵庫で冷やした方がより美味しくお召し上がりいただけます。
食べてみた
葛と白玉粉でもっちり食感に仕上げたういろうと甘い茹で小豆が美味しい一品です。
”夏越の祓”は、半年分の穢れを落として残り半年の健康と厄除けを祈願する行事です。人形流しや茅の輪くぐりなど実に様々な方法で心身を清めます。
そんな”夏越の祓”で食される水無月は、宮中で行なわれた「氷の節句」にちなんだ和菓子。当時超高級品だった氷を口にすることが出来ない庶民が、氷をかたどった三角形のういろうに魔よけの小豆を乗せたのが始まりなんだとか。
じめじめとした暑さで心身ともに弱りがちな季節。水無月のやさしい甘さで、心安らぐひとときをお過ごしください。
”夏越の祓”は、半年分の穢れを落として残り半年の健康と厄除けを祈願する行事です。人形流しや茅の輪くぐりなど実に様々な方法で心身を清めます。
そんな”夏越の祓”で食される水無月は、宮中で行なわれた「氷の節句」にちなんだ和菓子。当時超高級品だった氷を口にすることが出来ない庶民が、氷をかたどった三角形のういろうに魔よけの小豆を乗せたのが始まりなんだとか。
じめじめとした暑さで心身ともに弱りがちな季節。水無月のやさしい甘さで、心安らぐひとときをお過ごしください。
- 2022.03.22
- 11:38
よもぎの天ぷら
今しか収穫できない「よもぎの生葉」を、サクサク美味しい天ぷらに。
草餅・草団子はよもぎの香りや苦みと和菓子の甘みのハーモニーを楽しむものですが、こちらはよもぎそのものの風味を存分にご堪能いただけます。
草餅・草団子はよもぎの香りや苦みと和菓子の甘みのハーモニーを楽しむものですが、こちらはよもぎそのものの風味を存分にご堪能いただけます。

材料
よもぎの生葉:適量
卵:1個
冷水:200ml
薄力粉:140g
サラダ油(揚げ油):適量
卵:1個
冷水:200ml
薄力粉:140g
サラダ油(揚げ油):適量
作り方
下準備
よもぎの生葉は水で洗い、キッチンペーパー等で水気を拭き取る。
卵、薄力粉は使用する直前まで冷蔵庫でしっかり冷やしておく。
よもぎの生葉は水で洗い、キッチンペーパー等で水気を拭き取る。
卵、薄力粉は使用する直前まで冷蔵庫でしっかり冷やしておく。
調理
①揚げ物用の鍋にサラダ油を多めに入れ(7分目程度)、中火にかけて温めます。
②卵を溶いて冷水と混ぜ合わせ、さらに薄力粉を加えて混ぜ、衣を作ります。
③よもぎの生葉を食べやすい大きさにちぎり、②にくぐらせます。衣は薄めに付けた方がよりよもぎの色合いをお楽しみいただけます。
④温めたサラダ油に菜箸の先端を浸け、ぷくぷくと気泡が出始めたら③を油に入れます。この時、よもぎの生葉を油の中で泳がせるように軽く揺らすと、葉が開いて見栄えの良い天ぷらになります。
⑤よもぎ同士がくっつかないように注意しつつ、2~3分ほど揚げます。
⑥衣が焦げない程度に揚げ、余分な油をきったら完成です。
①揚げ物用の鍋にサラダ油を多めに入れ(7分目程度)、中火にかけて温めます。
②卵を溶いて冷水と混ぜ合わせ、さらに薄力粉を加えて混ぜ、衣を作ります。
③よもぎの生葉を食べやすい大きさにちぎり、②にくぐらせます。衣は薄めに付けた方がよりよもぎの色合いをお楽しみいただけます。
④温めたサラダ油に菜箸の先端を浸け、ぷくぷくと気泡が出始めたら③を油に入れます。この時、よもぎの生葉を油の中で泳がせるように軽く揺らすと、葉が開いて見栄えの良い天ぷらになります。
⑤よもぎ同士がくっつかないように注意しつつ、2~3分ほど揚げます。
⑥衣が焦げない程度に揚げ、余分な油をきったら完成です。
食べてみた
春にしか味わえない新鮮な生のよもぎを存分に堪能できるレシピです。
よもぎのほろ苦さを活かすため、塩だけつけて食べるのがおすすめです。うどんや蕎麦にトッピングして、めんつゆで食べても美味しいですよ。
よもぎのほろ苦さを活かすため、塩だけつけて食べるのがおすすめです。うどんや蕎麦にトッピングして、めんつゆで食べても美味しいですよ。
- 2022.03.22
- 11:41
ちまき
こどもの日・端午の節句にまつわる縁起物として愛されている和菓子、ちまき。
上新粉ともち粉で作って蒸しあげたもちもちのお餅に、笹の葉が爽やかに香ります。
上新粉ともち粉で作って蒸しあげたもちもちのお餅に、笹の葉が爽やかに香ります。

材料(5個分)
もち粉:100g
上新粉:30g
砂糖:50g
湯:60cc
笹の葉(軸付):10枚
タコ糸:適量
上新粉:30g
砂糖:50g
湯:60cc
笹の葉(軸付):10枚
タコ糸:適量
作り方
下準備
蒸し器に湯を沸かし、蒸気をあげておきます。
蒸し器に湯を沸かし、蒸気をあげておきます。
調理
①もち粉、上新粉、砂糖、湯を耐熱容器に入れ、混ぜます。
②1がまとまってきたらしっかり捏ねます。湯が足りない場合は適宜継ぎ足しながら、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで捏ねます。
③しっかり捏ねた生地を5等分にし、円錐状に成形します。(笹の葉の半分より少し短い程度の長さに整えてください)
④笹の葉で生地を包むように巻き、上からもう一枚笹の葉を被せて全体を包みます。
⑤笹の葉が開かないようにタコ糸で全体を縛ります。
⑥蒸気があがっている状態の蒸し器に⑤を並べ、笹の葉が変色するまで10~12分蒸したら完成です。
①もち粉、上新粉、砂糖、湯を耐熱容器に入れ、混ぜます。
②1がまとまってきたらしっかり捏ねます。湯が足りない場合は適宜継ぎ足しながら、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで捏ねます。
③しっかり捏ねた生地を5等分にし、円錐状に成形します。(笹の葉の半分より少し短い程度の長さに整えてください)
④笹の葉で生地を包むように巻き、上からもう一枚笹の葉を被せて全体を包みます。
⑤笹の葉が開かないようにタコ糸で全体を縛ります。
⑥蒸気があがっている状態の蒸し器に⑤を並べ、笹の葉が変色するまで10~12分蒸したら完成です。
食べてみた
砂糖と餅の素朴な甘さともちもちの食感が美味しいちまき餅になりました。
笹の葉で巻くことによって、香りも見た目も爽やかに。こどもの日・端午の節句を祝うのに欠かせない一品です。
笹の葉で巻くことによって、香りも見た目も爽やかに。こどもの日・端午の節句を祝うのに欠かせない一品です。
- 2022.03.22
- 11:23